毎月の重要な出費である「生命保険」
その生命保険の必要額を決める前に、まず確認しておきたいのが公的保障である「遺族年金」です。
公的な支えがどれくらいあるかを理解すると、民間の生命保険で「本当に必要な金額」が明確になり、必要以上な保険に入ることも防げます。
今回は、4人家庭の1例(夫:会社員/妻:専業主婦/子ども2人)をモデルに、実際の遺族年金の金額と注意点、そして遺族年金で不足しがちな出費を見ていきます。
そもそも、遺族年金とは?
遺族年金は、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、残された家族が受け取れる年金です。主に次の2種類があります。
- 遺族基礎年金:国民年金ベースで、子または子のいる配偶者向け
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方の家族向けの上乗せ分
条件や金額は加入履歴や子どもの有無・年齢などで変わりますが、「公的な最低限の生活を支える」ものです。
モデルケースで試算:実際いくらもらえる?
前提として、夫(会社員・年収600万円)、妻(専業主婦)、子ども2人(高校未満)を考えます。
遺族基礎年金の例
遺族基礎年金は、定額+子の加算があります。
- 基礎部分:829,300円/年
- 子の加算(子1人目、2人目):各239,300円/年
つまり、配偶者がまとめて受け取ると次の表のように、月額約11万円です。
| 区分 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金(基本額) | 831,700円 | 約69,308円 |
| 子の加算(1人目) | 239,300円 | 約19,941円 |
| 子の加算(2人目) | 239,300円 | 約19,941円 |
| 合計 | 1,307,900円 | 約109,190円 |
遺族厚生年金の例
遺族厚生年金の額は、厚生年金加入者向けに加算されるものです。
金額は、死亡した方の「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」、つまり老後に受給する年金の4分の3がベースです。
例えば、夫が年収600万円で、厚生年金加入期間20年の場合、遺族厚生年金は概算で年間約39万円、月額約3万円のイメージです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平均標準報酬月額 | 約400,000円(年収のうちボーナスを除いて月収40万円と仮定) |
| 老齢厚生年金の計算 | 400,000円 × 5.481/1000 × 240か月(20年) ≒ 526,176円(年額) |
| 遺族厚生年金 | 老齢厚生年金の3/4 → 約394,632円/年→約32,880円/月 |
遺族年金の合計としては…
今回の4人家庭(夫:会社員/妻:専業主婦/子ども2人)の場合、
遺族基礎 + 遺族厚生 ≒ 年額約170万円、月額約14万円程度です。
ただし、注意点としては、
- 子どもの年齢によって受給期間が変わる(遺族基礎年金は原則「子が18歳到達年度末まで」)
- 遺族厚生年金は厚生年金加入が前提。自営業などは対象外となるケースがある
- 再婚・就労・所得の変化で受給条件や金額が変わる
- 個別の事情で額が変動するため、最終的には年金事務所、ねんきんネット等で確認することが重要
遺族年金で足りない可能性が高い代表的な出費
遺族年金は生活の“最低ライン”をカバーしますが、以下の項目は不足しやすいです。
- 教育費(大学まで):子ども2人の学費は大きな負担
- 住居費(住宅ローンや賃貸家賃):団信のないローン残債がある場合や都心部の家賃は重い
- 老後資金:妻自身の将来の年金不足を補う必要が出る場合がある
- 生活のゆとり・予備費:習い事や急な医療費など
先の試算で「月14万円」は最低ラインの目安。教育費やローンを考慮すると不足する可能性が高いです。
遺族年金を踏まえた生命保険の考え方(アプローチ)
- 公的受給の把握:まず遺族年金でどれだけカバーできるかおおまかに把握(本記事のようなモデル試算)
- 主要支出の見積り:家賃(またはローン)、教育費、生活費のギャップを算出
- 不足分を民間保険で補填:定期保険や学資保険などで不足額を埋める(必要保障額から逆算)
- ライフプランの見直し:子どもの成長・収入の見込み・働き方の変化を踏まえて定期的に見直す
まとめ
遺族年金では「生活に必要な最低限度の保障」を得られる公的保障です。
しかし、教育費・住宅費・老後資金などを含めると、公的保障だけで十分とは言えないケースが多いです。
まず公的保障である「遺族年金」を正しく把握したうえで、不足分だけを民間の生命保険で補うアプローチが必要です。
具体的には、ねんきんネットで実際の加入履歴から、年金額のシミュレーションをするとよいでしょう。【日本年金機構ホームページ(ねんきんネットログイン):https://www.nenkin.go.jp/index.html】
「年金」「保険」と聞くとややこしくて難しいイメージですが、将来のために、具体的なイメージをもって考えていきたいですね!
※本記事は一般的な計算イメージを算出しましたが、具体の受給額は年金事務所・ねんきんネットで自分の状況に合わせてご確認ください。
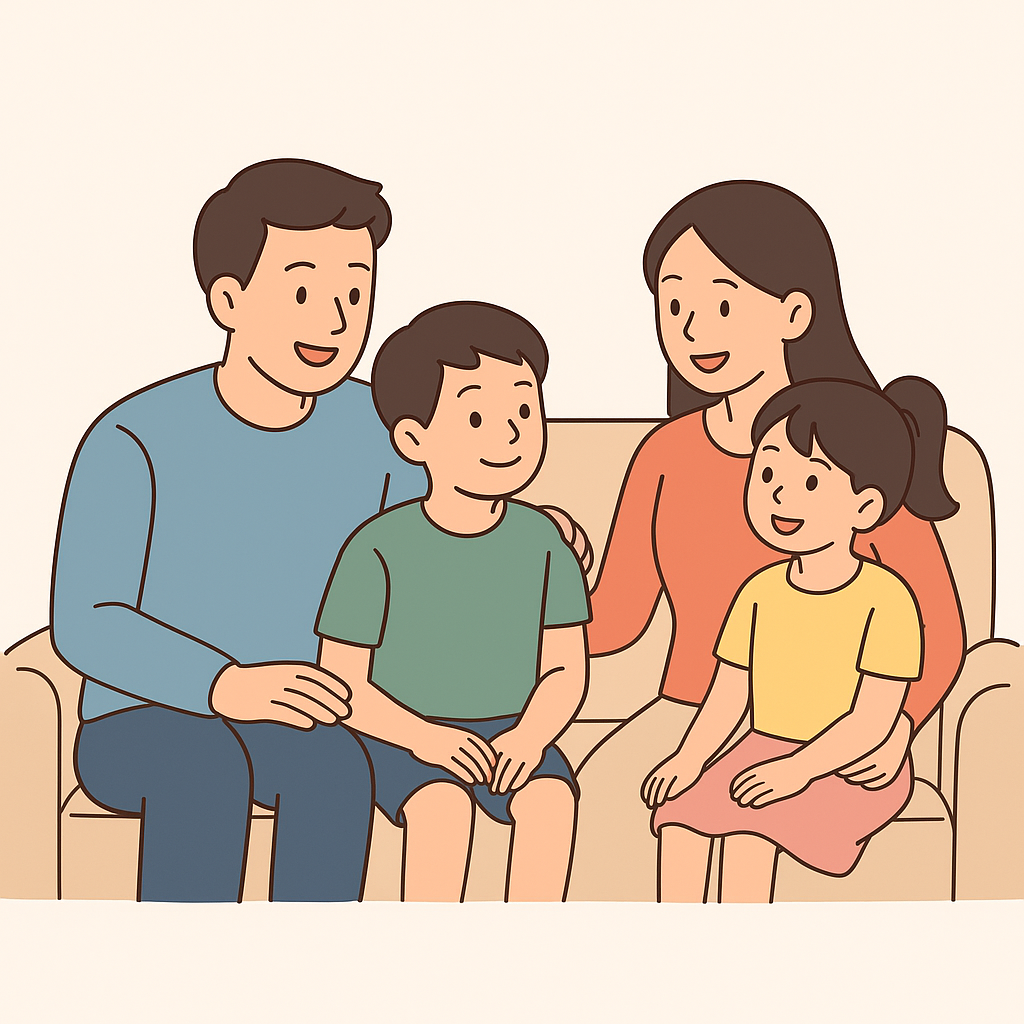


コメント