海外旅行や海外通販でクレジットカードを使うと、「海外利用手数料(海外事務処理手数料)」が発生します。カード会社ごとに手数料率が異なり、1〜3%ほどの差が出ることも。
そして海外利用手数料は、ここ1~2年で増加傾向です。
今回は、海外利用手数料の仕組みと、主要カードの最新の手数料を比較します。
海外利用手数料とは?仕組みをわかりやすく解説
海外利用手数料とは、海外でクレジットカードを使ったときに発生する手数料です。
例えば、海外で100ドルの商品をクレジットカードで購入します。
為替レートは1ドル150円とします。(支払い当日のレートとは少し時間差があり、VISAやMastercard等で処理するときのレートになります。)
手数料を含めないと「100ドル × 150円=15,000円」ですが、
これに海外利用手数料が3%の場合、「15,000円 × 1.03=15,450円」
手数料2%の場合、「15,000円 × 1.02=15,300円」となります。
このように同じ買い物でも、海外利用手数料の差1%で 150円の違い が生まれます。
主要クレジットカードの海外利用手数料を比較
それでは、主なクレジットカードの海外利用手数料を比較していきます。
| カード名 | 国際ブランド | 海外利用手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三井住友カード | VISA, Mastercard | 3.63% | 2024年11月~値上げ |
| 楽天カード | VISA, Mastercard, JCB, Amex | 3.63% | 2025年3月~値上げ |
| エポスカード | VISA | 3.85% | 2025年7月~値上げ |
| JCBカード(JCBカード W、original seriesなど) | JCB | 1.6% | |
| Amazonマスターカード | Mastercard | 2.2% | 2025年10月~値上げ |
| 住信SBIネット銀行のデビットカード | VISA, Mastercard | 2.5% | 米ドルなら年間30回まで手数料分をポイント還元 |
2024~2025年で、各社ともに海外利用手数料の値上げラッシュが続いています。
実際は、「海外利用手数料-クレカの還元率」で考えるべきですが、クレカの還元率(1~1.5%程度)よりも、海外利用手数料が高い場合が多いと思います。
エポスカードは、海外旅行保険が充実のエポスカードゴールドがありますが、手数料値上げの影響が大きいですね。。
JCBカードは、JCBが直接発行のカード(JCBカード W、JCB original seriesなど)が対象です。JCBブランドを選択した楽天カードなどは、その発行先(楽天カード)の手数料が適用されます。
海外利用手数料の節約方法
手数料が低いカードを持つ
手数料が安いカードを選ぶのが1つの方法です。比較表の中で安いカードはこちらでした。
- JCBカード・・・手数料1.6%で、低さが目立ちます。JCBが使えるお店であれば、JCBを使いたいですね。
- Amazonマスターカード(Amazon Primeマスターカード含む)・・・発行元は三井住友カードですが、このカードは手数料2.2%で低めです。
現金
「クレジットカードが高いなら、現金を使えばいいんじゃないの?」ということで、現金を両替する場合を考えます。
例えば、2025.11.14時点で成田空港の両替所(GPA)のホームページから、円から外貨に両替する場合の手数料を見てみます。
- 米ドル・・・¥→$157.44、$→¥150.74(往復6.7¥、片道3.35¥)なので、手数料2.1%
- ユーロ・・・¥→€183.96、€→¥175.26(往復8.7¥、片道4.35¥)なので、手数料2.4%
「海外利用手数料-クレカの還元率」と比較してみても、現金の方が安い場合が結構多いと思います。
注意点として、現金だと余った外貨を日本円に戻す場合も両替手数料がかかるので、両替する金額は最小限にしておきたいです。
デビットカード
比較表にあった住信SBIネット銀行のデビットカードは、米ドルで、年間30回以内であれば選択肢の一つです。
最近だと、Revolutなど、アプリを使ってデビットカードのように外貨引落が可能なサービスもあるようです。海外利用額が大きい場合は検討したいですね。
まとめ:海外利用手数料はカードごとに大きく違う
海外利用手数料は、カードによって差があり、しかも3%以上の手数料がかかる場合もあるため、海外旅行前に必ず確認したいですね。
海外旅行が多い人は、クレジットカード・現金・それ以外も検討して、納得して支払いをしていきたいですね。
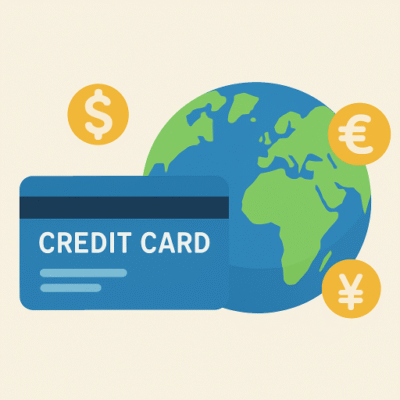


コメント